Time Nobleイメージ画像
グランドセイコーに資産価値はあるのか――これは時計好きならずとも、一度は気になるテーマだと思います。私自身、ロレックスやオメガ、タグ・ホイヤーなど数々の時計を所有してきた中で、グランドセイコーを選ぶかどうかはずいぶん迷った記憶があります。日本製の誇りともいえるこのブランドは、確かな品質と美しさを備えているものの、「リセールでは損するのでは?」という声がネット上でも目立つのが現実です。
たしかに、グランドセイコーはロレックスと比べると資産価値が低いという印象を持たれがちです。実際、「グランドセイコー やめとけ」「資産価値が下がる」などのネガティブな検索ワードが存在していることも事実です。ただ、すべてのモデルがそうかというとそうではなく、“資産価値が高まっているモデル”や、“将来的に価値が上がる可能性のあるモデル”があるのもまた事実です。
私の経験では、モデル選びとタイミングを見極めることで、グランドセイコーは十分に資産性を持ち得るブランドだと実感しています。特に限定モデルや希少性の高いダイヤル、スプリングドライブ搭載機種などは、市場での評価が安定または上昇傾向にあります。
この記事では、グランドセイコーの資産価値にまつわる真実を掘り下げ、実際に価値が上がったモデルや、逆にリセールが厳しいモデルの傾向、そして後悔しないための“損しない選び方”まで、実体験をもとに解説していきます。購入を検討している方にとって、少しでも指針になるような内容をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事でわかること
・グランドセイコーに資産価値はあるのか?リセール事情の実態
・今後価値が上がる可能性のある注目モデル
・資産価値を意識した時計の選び方とタイミング
・買って損するモデルの特徴と注意点
グランドセイコー 資産価値の実態と評価されるモデルの特徴

「グランドセイコーに資産価値はあるのか?」という問いに対して、世間の評価は分かれています。一部では「リセールが悪いからやめとけ」と言われることもありますし、一方でコレクターの間では「むしろ今が買い時」と語られる場面も増えてきました。実際、私が時計好きとして複数のブランドを所有してきた経験の中でも、グランドセイコーは“選び方次第で資産性が大きく変わるブランド”だと強く感じています。
ロレックスのように、ブランドそのものが資産であるというタイプとは異なり、グランドセイコーの価値は“中身”と“背景”にあると言っていいでしょう。手間暇かけて作られる仕上げ、独自のスプリングドライブ、伝統と革新が融合したデザイン。これらに共感できるかどうかで、評価も大きく変わってきます。
私自身も、かつては「グランドセイコーは損するんじゃないか」と半信半疑で手を出しました。しかし、使い続けるうちにその価値に気づき、結果的に市場価格が上がっていたというモデルもいくつかあります。「資産価値」とは何も転売益だけではなく、「価値が落ちにくい」「安心して持てる」「持ち主の満足感が持続する」といった面も含まれるとすれば、グランドセイコーは非常に優れたブランドなのではないかと今では思っています。
ここでは、グランドセイコーの資産価値にまつわるリアルな評価と、実際に“価値が上がった”あるいは“安定している”モデルの特徴について掘り下げていきます。ブランドの背景やマーケットの動きをふまえ、どのような視点で見れば損しにくい選択ができるのか、順を追って解説していきます。
・グランドセイコーは資産価値が低いと言われる理由とは?
→ ロレックスとのリセール率の差、知名度の影響、ブランド戦略など
・資産価値が高まるグランドセイコーの特徴とは?
→ 希少性、限定モデル、搭載ムーブメント(スプリングドライブなど)
・実際に価値が上がったグランドセイコーのモデル事例
→ SBGW047、SBGA125、銀座限定などのプレミア事例を紹介
・「やめとけ」と言われるモデルは本当に損なのか?
→ 評判が悪い型番や選ばれ方の失敗事例を中立に解説
・リセール率はどれくらい?ロレックス・オメガとの比較
→ 平均買取率や再販価格を他ブランドと比較し現実を可視化
グランドセイコーは資産価値が低いと言われる理由とは?
「グランドセイコーは資産価値が低いからやめとけ」と言われる理由は、いくつかの現実的な要因に基づいています。私自身も購入前に散々この意見を目にして不安になった一人ですが、実際に調べ、使い、そして手放した経験を通してその“根拠”が見えてきました。
まず1つ目の理由は、「再販市場でのブランド力の違い」です。たとえばロレックスやオーデマ・ピゲのように、“持っているだけで価値がある”という認識が広く浸透しているブランドと比較すると、グランドセイコーはまだ知名度やブランドイメージの点で劣ると感じられてしまいます。とくに海外では「セイコー=安い時計」というイメージが根強く、その印象がリセールにも影響を与えているのです。
2つ目は、供給量とモデル数の多さです。グランドセイコーは限定モデル以外でも多くのバリエーションを展開しており、型番の整理がしにくいという点もあります。ロレックスのように「○○番は希少」と明確に語られる機会が少なく、モデルの違いがわかりにくいことで価格差も生まれにくくなります。
また、3つ目に「時計としての価値は高いのに、資産としての認知が進んでいない」というギャップも見逃せません。職人による手仕上げ、スプリングドライブのような革新的技術、文字盤の美しさなど、内面のクオリティは非常に高い。しかしそれが“市場価値=お金”に直結しにくい現状が、「価値が低い」と言われる要因になっています。
ただし、これは“すべてのモデルが低い”という話ではありません。価値が低くなりやすいモデルもあれば、しっかりと価格を維持・上昇させているモデルもあるのがグランドセイコーの特徴です。その違いを理解しておけば、「やめとけ」と言われる時計の中にも、自分にとって“後悔しない資産”が眠っていることに気づけるはずです。
資産価値が高まるグランドセイコーの特徴とは?
「グランドセイコーはリセールが弱い」と言われがちですが、すべてのモデルがそうとは限りません。実は、資産価値が高まりやすい“傾向”を持ったモデルには明確な共通点があります。私自身もこの数年で複数のグランドセイコーを手にしてきましたが、資産価値が安定しているモデルにはいくつかの条件が揃っていました。
まず注目したいのが、数量限定モデルです。特に“国内○本限定”や“ブティック限定”といった販売チャネルが限られているモデルは、その希少性が中古市場での価格維持に大きく影響します。たとえば、銀座限定や周年記念モデルなどはリリース直後から注目されることが多く、未使用品は定価以上で取引されることもありました。
次に、ダイヤルの個性や技術の高さも重要です。グランドセイコーは“雪白ダイヤル”や“四季ダイヤル”など、視覚的に美しく、ブランドのアイデンティティを強く感じられる文字盤を得意としています。こうしたモデルは、SNSやYouTubeでも話題になりやすく、注目度が価格を支える役割を果たしています。
そして、スプリングドライブやハイビートムーブメントといった独自技術を搭載したモデルも資産性が高まりやすい傾向があります。とくに9R系ムーブメントや9S系ハイビートは、単なる「セイコーの上位機種」ではなく、「世界に通用する精密機械」としての魅力が評価され、将来的な価値の上昇が見込まれる要素です。
さらに、**ケースサイズとデザインの“普遍性”**も見逃せません。大ぶりすぎず、ビジネスシーンでも違和感のないサイズ(37〜40mm前後)や、クラシカルなデザインは長く市場に評価される傾向があります。あまりに流行寄りのデザインは数年で古さを感じさせてしまい、価値の維持が難しくなるため注意が必要です。
こうしたポイントを押さえることで、グランドセイコーの中でも“資産としての魅力”が強いモデルを見極めることができます。つまり、「グランドセイコーだから資産価値が低い」のではなく、「何を選ぶか」で結果がまったく変わってくるというのが、私の実感です。
実際に価値が上がったグランドセイコーのモデル事例
「グランドセイコーに資産価値はある」と実感できるのは、やはり実際に価値が上がったモデルの事例を知ったときです。私自身も一時期、複数のモデルの相場をウォッチしていたことがあり、その中で「これは明らかに価格が上がっている」と気づいたモデルがいくつか存在します。以下はその中でも特に印象に残っているものです。
まず代表的なのが、SBGW047。これは2013年に国内限定300本で発売されたモデルで、シルバーのケースと上品なブルーインデックスが特徴的な手巻き3針。発売当初は定価で25万円程度だったにもかかわらず、現在では美品が40〜50万円以上で取引されるケースも珍しくありません。希少性とデザインの完成度が、まさに“後から評価される”典型例です。
次に挙げたいのが、SBGA125(銀座限定モデル)。こちらはグランドセイコー銀座ブティックのみでの取り扱いで、“銀座の街並み”をモチーフにした独自のダイヤルパターンが魅力です。限定数は100本。リリース後すぐに完売し、その後も中古市場ではなかなか出回らず、価格も常に高値を維持しています。まさに「知る人ぞ知る資産モデル」です。
他にも、**SBGA211(通称:雪白ダイヤル)**はリリース当初からの人気を保ちつつ、今ではグランドセイコーを象徴する存在になり、国内外問わずファンが多いモデルです。生産終了の噂もあったことで一時価格が上がり、安定的なリセールを実現している数少ない“定番かつ資産性”のあるモデルといえます。
また最近では、海外で注目されている**U.S.エディション(米国限定モデル)**にも高い資産性が見込まれており、海外市場における評価の高まりが、将来的な価格上昇に拍車をかける可能性があります。
これらのモデルに共通しているのは、希少性・デザイン性・語れるストーリーです。単に高級時計というだけでなく、「なぜこのモデルが特別なのか」が明確であることが、資産価値の高まりに直結しているように感じます。
「やめとけ」と言われるモデルは本当に損なのか?
「グランドセイコーはやめとけ」と言われることがありますが、なぜそう言われるのでしょうか。そしてその声は、本当に信じるべきものなのでしょうか。私も購入前、この言葉にかなり影響を受けた一人でしたが、結論から言えば“すべてのモデルが損”というわけではなく、「選び方次第」で評価は大きく変わります。
まず、「やめとけ」と言われがちなモデルの特徴を挙げてみます。共通しているのは、大量生産モデルや汎用デザイン、特徴に乏しい文字盤のもの。例えば、機械式ではなくクオーツで価格帯も比較的抑えめなモデルは、「グランドセイコーの魅力=職人技やムーブメントの完成度」を感じにくく、中古市場では値崩れしやすい傾向があります。
また、リファレンス番号(型番)による違いを知らずに購入してしまうケースも、後悔の原因になります。似たような見た目でも、9Fクオーツと9Rスプリングドライブ、9Sメカニカルでは価格帯もリセール価値もまったく異なります。にもかかわらず、見た目や価格だけで選んでしまうと「期待外れだった」「手放すときに二束三文だった」と感じることになってしまうのです。
さらに、“最新モデル=将来的に価値が上がる”という先入観で買ってしまうのも要注意です。グランドセイコーの場合、限定性や背景にストーリーのあるモデルでなければ、発売直後は値下がりすることが一般的です。私も過去に、発売直後のノン限定モデルを定価で購入し、半年後に手放した際は3割以上の価格差に愕然とした経験があります。
しかし、これらの失敗はあくまで「選び方」を間違えた結果であり、グランドセイコーというブランドそのものの価値とは別問題です。資産価値を意識するなら、限定性・ムーブメント・仕上げの細かさといった本質的な要素を重視すれば、十分に“損しない選び方”が可能になります。
つまり、「やめとけ」という評価は一部のモデルや買い方に対するものであり、正しい知識と視点を持っていれば、グランドセイコーでも後悔しない買い物ができるというのが私の実感です。
リセール率はどれくらい?ロレックス・オメガとの比較
グランドセイコーの資産価値を語るうえで欠かせないのが「リセール率」です。いわゆる“売ったときにどれくらい戻ってくるか”というこの指標は、時計を資産として考える際に最も現実的な基準の一つです。そして、よく比較されるのがロレックスやオメガといった他の人気ブランドとの違いです。
まず、ロレックスは別格です。新品で買っても中古で同額〜プレミア価格で売れるモデルが多く、リセール率は80%〜100%超という驚異的な数値を記録することも珍しくありません。特にサブマリーナ、デイトナ、GMTマスターなどの人気モデルは、中古市場でも常に需要があります。
一方、オメガはモデルによりますが、シーマスターやスピードマスターといった主力ラインは60%前後のリセール率が期待できます。限定モデルで状態が良ければもう少し上がることもありますが、ロレックスほどの安定感はありません。
そしてグランドセイコー。結論から言うと、一般的なモデルでのリセール率は40〜55%程度にとどまることが多いです。特に汎用モデルやクオーツ式は、定価の半額以下になることも少なくありません。私が以前、40万円で購入したスタンダードなスプリングドライブモデルは、1年後の下取り価格が約18万円と提示された経験もあります。
ただし、これがすべてのグランドセイコーに当てはまるわけではありません。前述のように、限定モデルや希少仕様は70%以上のリセール率を保っているケースもあり、2020年代以降は市場の注目度も少しずつ変化し始めています。
つまり、ブランド全体のリセール率だけを見て「資産価値が低い」と判断するのは早計です。グランドセイコーは“ピンポイントで資産性が高いモデルが存在する”ブランドであり、それを見極める力が必要だと私は感じています。
グランドセイコー 資産価値を意識した“損しない選び方”と今後の注目モデル
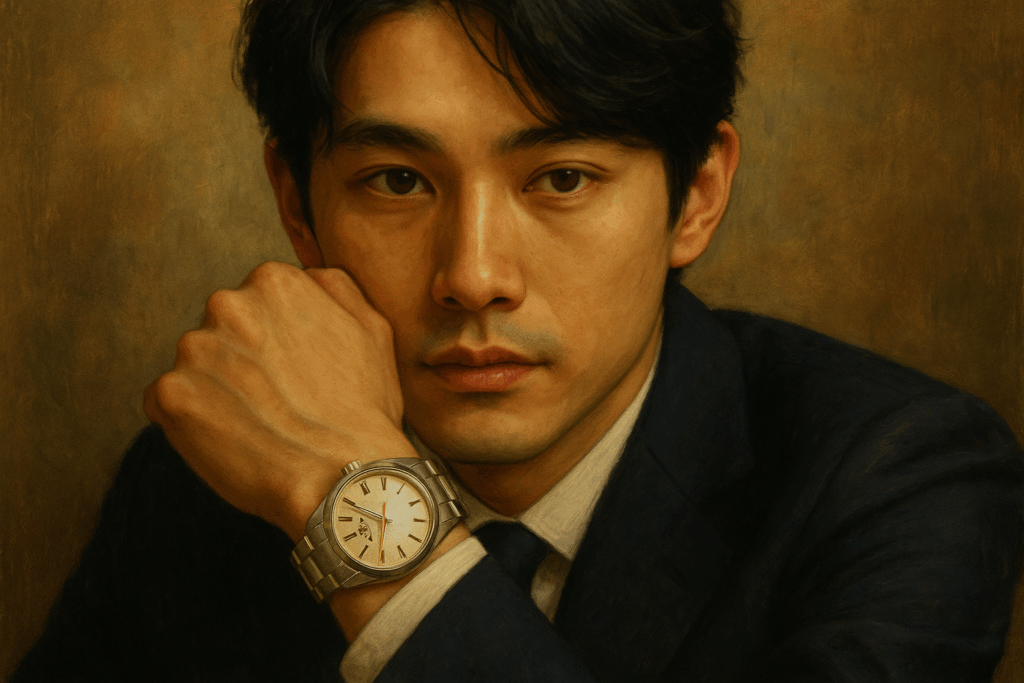
ここまでで、グランドセイコーの資産価値は「低い」と言われながらも、選び方によっては大きく評価が変わることをお伝えしてきました。実際に私が見てきた中でも、リセール率が振るわなかったモデルもあれば、想定以上に値上がりしたモデルもあり、その差は“買う前の判断軸”によって決まっていたと言っても過言ではありません。
グランドセイコーは、ロレックスのように“全体的に安定して高い資産価値を維持するブランド”ではなく、“モデルごとに明暗が分かれるブランド”です。だからこそ、「どのモデルを選ぶか」「どの視点で選ぶか」が極めて重要になります。私もかつて、「スペックが良さそうだから」とだけで選んだモデルで痛い目を見た経験がありました。それ以来、資産性を意識する際には、単なる機能や見た目以上に「流通数」「限定性」「海外での評価」など、複数の視点で総合的に判断するようにしています。
この後のセクションでは、「損しない選び方」を実際の経験と情報に基づいて分かりやすく整理していきます。具体的には、どのようなモデルが将来価値を持ちやすいのか、リセールを意識するなら避けるべきポイントはどこなのか。そして、今注目すべき“これから伸びそうなモデル”とは何か。これらを通して、グランドセイコーを「買ってよかった」と心から思える一本に出会うための考え方を共有していきます。
・リセールを意識するなら外せない3つの選び方
→ 型番、限定性、ムーブメント(メカニカル or スプリングドライブ)
・値上がりが期待できる?今注目されている現行モデル
→ 製造終了の可能性がある型・裏スケ・クラシック路線の評価上昇など
・中古で買うべきか、新品で買うべきか?価格差と資産性の違い
→ 中古の初期価格下落・新品プレミア予測の視点から分析
・投資目的で買うと後悔する?私の失敗と成功体験から学ぶ
→ 「好きで買う」ことと「値上がるから買う」の間にある違い
・将来の価値が育つ時計とは?“資産価値を超える”選び方の本質
→ 長く使い込めるもの・自分の価値観に合うものの重要性を強調
リセールを意識するなら外せない3つの選び方
グランドセイコーを「損せずに買う」ためには、資産価値が残りやすいモデルを見極めることが不可欠です。私自身も何度か“失敗”を経験したからこそ、いまはこの3つのポイントを重視するようにしています。どれも単純なスペック比較では分かりにくいですが、長期的に満足感と価値を両立させるうえで非常に有効です。
① 限定性のあるモデルを狙う
市場に出回る数が限られているモデルは、それだけで希少性という価値が生まれます。たとえば「銀座限定」「100本限定」「アニバーサリーモデル」といった記念的な位置づけのモデルは、再販がないぶんプレミア価格がつきやすい傾向があります。私も以前、限定300本のモデルを購入し、2年後にほぼ定価に近い金額で手放せたことがありました。
② 独自ムーブメント搭載モデルを選ぶ
グランドセイコーには「スプリングドライブ」や「ハイビート(9S)」など、世界的にも注目されるムーブメントがいくつかあります。これらを搭載したモデルは、時計ファンやコレクターの関心も高く、機能だけでなく“語れる要素”としての魅力も加わります。単なる外見やブランドイメージだけでなく、内部に価値があるモデルは、資産としても強いと感じています。
③ 普遍的なデザインとサイズを選ぶ
流行り廃りの少ないデザインは、長く価値を保ちやすいです。ビジネスでも使えるクラシカルな3針モデル、視認性の高いシンプルなダイヤル、ケース径37〜40mm前後のバランス感のあるサイズ感。このあたりは中古市場でも需要が安定しやすく、「売るときに選ばれやすい」ポイントになります。
この3つの選び方を意識するだけで、グランドセイコーの中でも“買って後悔しないモデル”がかなり絞れてきます。見た目の好みももちろん大切ですが、資産価値を気にするのであれば、「好き」だけでなく「残る」選び方を心がけることが、後悔しないコツです。
値上がりが期待できる?今注目されている現行モデル
グランドセイコーの中でも、「今後価値が上がるかもしれない」と注目されている現行モデルは確かに存在します。私自身も、最近の市場動向や中古相場を日常的に追っている中で、「これは将来的に化けそうだ」と感じるモデルにはいくつかの共通点があることに気づきました。ここでは、今“あえて買っておきたい”注目モデルとその理由をご紹介します。
まず注目されているのが、SBGW231。これはクラシックな37.3mmのケースサイズに手巻きムーブメントを搭載した、グランドセイコーらしい“原点回帰”モデル。レトロでありながら現代的な完成度を持ち、スーツにもカジュアルにも馴染む懐の深さが特徴です。現行ラインでありながら、生産終了の噂も一部で囁かれており、値上がりの兆候が見え始めています。
次に、**雪白ダイヤル(SBGA211)**は今なお根強い人気を保っているモデルです。アメリカ市場でも「Snowflake」の愛称で親しまれ、和の美意識が込められた独特のダイヤルパターンは世界中のコレクターに注目されています。新作モデルのリリースとともに「旧モデルの希少性」が意識され、徐々に中古価格も下支えされてきています。
また、**U.S.エディション(SBGA471など)**のような海外限定モデルも見逃せません。海外でしか流通していないモデルは日本国内での入手が難しく、それが逆にプレミア感を生んでいます。円安傾向や海外人気の高まりを背景に、こうしたモデルは今後の価格上昇候補として注目すべき存在です。
さらに、最近注目度が高まっているのが、“四季”シリーズなどのコンセプトダイヤル系モデル。視覚的に強い個性を持ちつつもグランドセイコーの上質感を損なわず、かつ製造数がそれほど多くない点が魅力です。SNS映えしやすいビジュアルも人気を後押ししています。
こうしたモデルに共通するのは、デザインの完成度、ストーリー性、限定感や海外評価です。目先のスペックに惑わされず、「5年後にも評価されるかどうか?」という視点で選ぶことが、結果的に“資産価値が育つ時計”を手にする近道になると私は考えています。
中古で買うべきか、新品で買うべきか?価格差と資産性の違い
グランドセイコーを購入する際、多くの人が悩むのが「新品で買うべきか?それとも中古が得か?」という問題です。私も最初の1本を選ぶときに相当迷いましたし、結果的に“中古と新品の両方”を経験したからこそ、それぞれのメリット・デメリットがはっきりと見えてきました。
まず、新品のメリットは当然ながら「安心感」と「最新状態」が得られることです。正規店やグランドセイコーブティックで購入すれば、正規保証がつき、状態も完璧。初期不良やトラブルのリスクがなく、アフターサービスもスムーズに受けられます。また、自分の所有履歴が“最初”という点で、愛着を持って長く付き合いやすいというのも精神的に大きな魅力です。
一方で、新品には「買った瞬間に価格が下がる」という明確なデメリットがあります。グランドセイコーの多くのモデルは、購入直後に中古市場での価格が定価の60〜70%程度にまで落ちるのが一般的で、特に限定モデルでない場合は短期的に損をする可能性が高いのです。私も過去に、40万円で新品購入したモデルを1年後に手放した際、査定額が22万円だったことがあります。
対して、中古市場では“すでに値下がりしきった価格”で購入できるため、再販売時のリスクが低くなります。特に「美品」や「保証書・箱付き」の個体をうまく探せば、新品同様の使用感を大幅に安く手に入れることが可能です。最近では正規店並みに状態を管理している中古専門店も増えており、実は初めての1本に中古を選ぶ人も珍しくありません。
ただし、中古で気をつけるべきは「どのモデルを選ぶか」と「どこで買うか」。信頼できる販売店を選び、製造年やムーブメントのコンディション、保証の有無などをしっかりチェックすることが前提です。また、モデルによっては年式の古さが価値に影響する場合もあるため、資産性を求めるなら“相場より安すぎるもの”には注意が必要です。
まとめると、「少しでも安く、損したくない」なら中古が向いており、「新品の状態や所有体験を重視する」なら新品を選ぶべきです。資産価値の観点で言えば、“状態の良い中古を賢く選ぶ”ことが、もっとも効率の良い選択肢だと私は感じています。
投資目的で買うと後悔する?私の失敗と成功体験から学ぶ
資産価値を意識して時計を選ぶとき、誰もが一度は考えるのが「投資として買っても儲かるのか?」という視点です。私もかつて、「このモデルは値上がりするかも」と思ってグランドセイコーを選んだことがあります。けれど結論から言えば、**“投資目的で買うと後悔する可能性が高い”**と今では感じています。
私が過去に経験した「失敗」は、ある限定モデルのスプリングドライブ。ネットでは「入手困難」「プレミア確実」と話題になっていたので、これはチャンスだと飛びつきました。しかし、いざ市場に出回ると意外にも在庫が潤沢に残っており、定価以下で売られている状況が続きました。期待値だけで動いた結果、結局は数万円の損を出して手放すことに。購入前に“供給数”や“販売戦略”をもっと冷静に見ておくべきだったと痛感しました。
一方で、思いがけず「結果的に成功した」体験もあります。それは、資産価値など気にせず、純粋に気に入って買った手巻きのクラシックモデル(SBGW047)でした。当時は市場の注目度も低く、単に“デザインと造りが好みだった”という理由で選びました。ところが数年後、希少性が評価されて中古市場で価格が上昇。今では購入価格を上回る査定を受けるほどになっています。
この2つの体験から私が学んだのは、「好き」で選んだ時計は手放したくならないし、持ち続けることで結果的に資産になることもあるということ。そして、投資目的で買うと、価格の動きに一喜一憂しがちで、着ける楽しさより“損得勘定”ばかりが気になってしまうというデメリットもあるのです。
もちろん、「投資的な視点」を持つこと自体は悪いことではありません。むしろ、資産価値という観点で“損しない買い物”を意識するのは今の時代には必要な判断です。ただし、それだけに偏ると「時計本来の魅力」から遠ざかってしまう。グランドセイコーのような“使ってこそ味わえる美しさ”を持つ時計ならなおさら、自分の感性を信じる選び方が、結果として後悔しない道につながると私は思います。
将来の価値が育つ時計とは?“資産価値を超える”選び方の本質
グランドセイコーのような時計を「資産」として捉えることは、もちろん大切な視点です。ですが私自身、長く時計と付き合ってきて感じるのは、本当に価値が“育つ”時計というのは、数字だけでは測れないということです。資産価値を超える“所有価値”というものが、確かに存在するのです。
たとえば、手巻きのクラシックモデル。買った当初は正直なところ、派手さもなく“地味すぎたかも”と感じていたのですが、日々使っていくうちに、その穏やかな美しさや巻き心地、時間の見やすさに魅了されていきました。何より、“自分で時間を巻く”という行為が生活のリズムになり、単なる機械ではなく“人生を共にする存在”のように感じられるようになったのです。
そうした“愛着”の積み重ねが、結果的にその時計を「手放したくないもの」にし、資産価値以上の満足感を生み出してくれます。これは、どれだけリセール率が高くても、「あまり気に入っていなかったモデル」では得られない感覚です。
もちろん、資産価値を意識して選ぶことは悪いことではありません。むしろ今の時代、再販のしやすさやリセール時の価格は重要な判断材料になります。ですが、それだけを基準に時計を選ぶと、本当の意味で「長く持てる」一本には出会いにくいのではないかと私は思うのです。
将来価値が育つ時計とは、“所有者の中で価値が深まっていく時計”です。買ったときの喜び、日々使う中での満足感、そして時間とともに生まれる物語。そういった感情の積み重ねこそが、グランドセイコーのようなブランドの本質であり、数字では表せない“資産以上の価値”になるのです。
選ぶときには、スペックや価格だけでなく、「自分の人生にどうフィットするか」という視点を持ってみてください。その一本は、きっと“価値が育つ”存在になるはずです。
まとめ|グランドセイコー 資産価値を考えるなら、“選び方”がすべてを左右する
グランドセイコーに資産価値があるのか? という問いに対しての答えは、「モデルと選び方による」というのがこの記事の結論です。ロレックスのように“どのモデルを買っても安定して高値がつく”というわけではありませんが、グランドセイコーにも確実に“資産性を持ちうる一本”が存在します。
実際に、限定モデルや希少ダイヤル、スプリングドライブ搭載機種などは、時間とともに中古相場が上がったり、高値で取引されているケースも珍しくありません。一方で、供給量の多い汎用モデルや差別化の薄いデザインのものは、リセールで苦戦しやすいのも事実です。
だからこそ、グランドセイコーの資産価値を正しく見極めるためには、「どれを選ぶか」以上に、「なぜそれを選ぶのか」を明確にしておくことが大切です。単なる投資目的ではなく、自分の価値観やライフスタイルと噛み合う一本を選んだとき、その時計は数字以上の価値を持ち始めます。
この記事で紹介した“損しない選び方”をもとに、自分だけの一本と出会えれば、グランドセイコーはきっと“資産価値のある買い物”になります。そしてそれは、手放すことなく長く付き合うほどに、ますます価値が深まっていく時計にもなっていくはずです。



